川崎、宮古、大江工場、相次ぎ操業を開始
自動車用、機械用、車両用バネの注文は日を追うごとに目覚ましい勢いで伸び、帝発工場の売上高は1935年の約140万円から、わずか4年後の1939年には450万円を突破するほど急増しました。
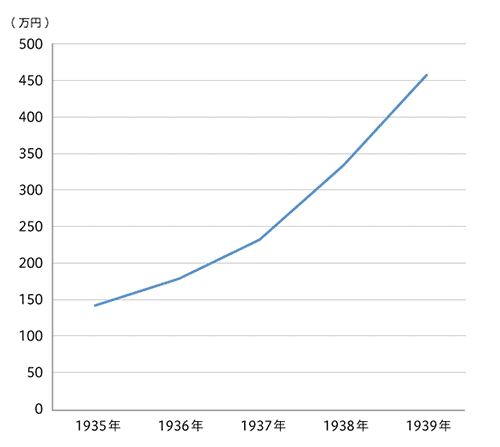 帝発工場売上高推移
帝発工場売上高推移急速なバネ需要の増加に対応するため、1938年には新たに川崎工場の建設に踏み切り、翌年6月から操業を開始。直後の同年7月、帝発工場は熱田工場とともに工場事業場管理令により軍の共同管理下に置かれました。1940年の本格稼働を機にバネ専門工場の川崎工場は正式に誕生、それと同時に帝発工場は東京工場と改称されました。川崎工場は従業員70名、板バネ500トン、巻きバネ100トンの生産能力を持つ工場として発足。川崎工場もまた、操業開始から間もない同年8月に工場事業場管理令により軍の管理下に置かれ、兵器用バネの増産にも対応することとなりました。その結果、東京、川崎の両工場は軍需に対応しながら、その生産量を伸ばしていきました。
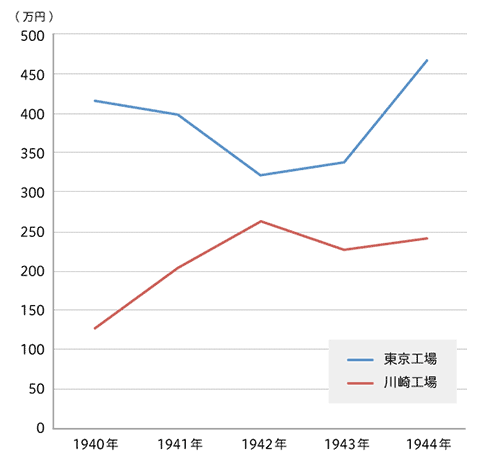 バネ生産高推移
バネ生産高推移1938年には築地、熱田両工場の合金鉄製造設備が星崎工場に集約され、当社は福島工場、星崎工場の2工場体制で合金鉄の増産を図りましたが、急増する需要を賄うには至りませんでした。当社は、合金鉄専門工場として宮古工場(岩手県)の新設を決定し、1939年にフェロシリコンの生産を開始。宮古工場は引き続き拡張工事に着手し、1942年にはフェロマンガンも生産品目に加わり、同工場の生産量は1944年に2,200トンを突破しました。
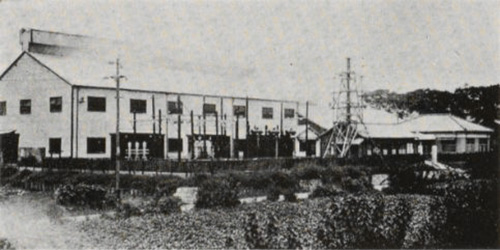 宮古工場(1939年)
宮古工場(1939年)鋳鋼専門工場にシフトした熱田工場の敷地が狭くなったことと電気炉の需要急増に対応するため、1939年に電気炉製作専門工場を新たに建設することを決定しました。星崎工場の近くに約8万平方メートルの用地を買収し、工場建設に着手。大江工場と命名された新工場は1940年に操業を開始。大江工場の操業開始当初は中国、満州からの受注急増に対応するため生産高はめざましい伸びを見せましたが、資材の入手が困難になり始めた1942年を境に同工場の生産高は一進一退の状況が続きました。
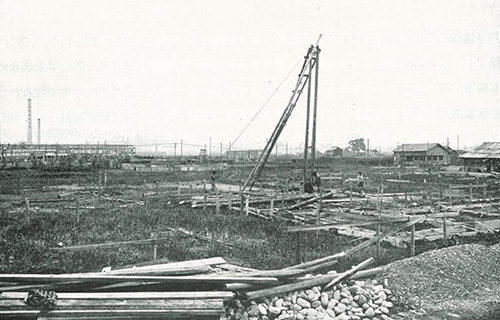 建設当時の大江工場(1939年)
建設当時の大江工場(1939年)






